
いつもの買い物をおトクに、ちょっと良いことも。「三方よし」でクラダシが目指す、ソーシャルグッドの姿
お菓子や飲み物、調味料から生鮮食品、日用品など、幅広い商品を取り扱うソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」。その価格を見てみると、中には定価から8割近く値引きされたものもあり驚きます。
つい、いろいろな商品を探したくなるお値段の秘密は、まだ食べることができるのに廃棄されてしまう「フードロス」になる可能性があるものを扱っているところにあります。
「日本では、年間472万トン以上の食料がまだ食べられるにもかかわらず廃棄されています(農林水産省2024年6月発表時点)。その理由は、パッケージの不具合、賞味期限の切迫、クリスマスなどのイベント終了に伴うものなどさまざまですが、まだ美味しく食べられることには変わりありません。Kuradashiは、そんな通常ルートで販売が困難な商品をおトクな価格で販売し、その売り上げの一部で社会貢献活動を支援しているECサイトなんです」
そう話すのは、Kuradashiを運営するクラダシの代表取締役社長CEO、河村晃平さんです。
2023年6月30日、東京証券取引所グロース市場へ上場したクラダシは、「日本で最もフードロスを削減する会社」を目指し、事業を展開しています。その内容や、クラダシが目指したい姿について伺いました。
河村 晃平(かわむら こうへい)さんプロフィール
1985年生まれ。早稲田大学を卒業後、2009年より豊田通商株式会社にて自動車ディーラー事業に従事。5年間の中国駐在ののち、株式会社Loco Partnersの執行役員を経て、2019年6月にクラダシに入社、2022年7月に取締役執行役員CEOを経て、2024年7月1日付けで代表取締役社長CEOに就任。
ブランド価値も守る「1.5次流通」
-クラダシの創業の背景と、河村さんが参画した経緯を教えてください。
クラダシは、前社長である関藤竜也が創業しました。私が最初に関藤と出会ったのは、2012年の夏、北京でのこと。クラダシ創業の2年ほど前になります。
阪神淡路大震災を経験した関藤は、当時、震災の支援活動を行っていました。その中で、一人でできる限界を強く感じ、社会課題を「仕組み」で解決する必要性を痛感したと関藤は言います。また関藤は、前職の商社で中国に赴任していた時に大量生産・大量廃棄の問題を目の当たりにし、「いつか資源が枯渇し、大きな社会課題になるだろう」と考えました。そして、2014年に創業したのが「フードロスを持続可能な仕組みによって解決する」クラダシです。
私も商社にいたこともあり、仕事をする中で「この先も皆が幸せに暮らせる環境や社会を、ビジネスで実現する方法があるのではないか」と漠然と感じていました。そうしたタイミングで関藤と出会い、「大きな課題を仕組みで解決する」というクラダシのビジネススキームに共感して、クラダシに参画する決意をしました。

-クラダシは、累計1,900社以上のパートナー企業の商品を販売していますよね。食品メーカーがフードロスを削減するハードルや課題は、どのようなところにあるのでしょうか。
日本のフードロスの市場規模は、8,500億円くらいだと言われています。フードロスを減らすための企業努力をしていても、これだけ発生してしまうのです。
その背景は、需給予測が難しいという点にあります。企業は生活者がどれだけものを必要としているのか予測しながら生産を行いますが、完璧にはできないため、フードロスをゼロにすることは難しいのです。
また、環境課題に対する企業の取り組みが注目される中、「廃棄」という行動は企業イメージの毀損になってしまいます。一方で、食品メーカーの自社サイトなどでフードロスになる懸念がある商品を安価で販売しようとすると、正規の値段との乖離が大きくなり、お客さまが混乱してしまう懸念があるというジレンマがあります。
-クラダシは、「1.5次流通」でその悩みを解決しているんですね。
そうですね。1.5次流通は、企業からお客さまへの販売である1次流通と、一度市場に出た商品がオークションやフリマアプリなどを通じて再び販売される2次流通の中間という意味で、廃棄の可能性があった商品を価値あるものに生まれ変わらせ市場に提供することを指します。食品メーカーは正規の価格で売り切る努力をし、それでもフードロスになる懸念が発生した時の流通をクラダシが担うという棲み分けを行うことで、ブランド価値の維持とフードロスの問題を解決しています。
-「3分の1ルール」という、メーカーが小売へ納品する時の商慣習がフードロスの一因であるとも聞きます。
3分の1ルールは、スーパーやコンビニなどの小売側の事情や、生活者のニーズから生まれた商慣習です。小売側からすれば、賞味期限が長い=販売できる期間が長い方が効率的ですし、生活者としては、なるべく賞味期限が長いものを購入したいという方もいらっしゃいます。そのため、たとえば製造日から賞味期限が90日間の商品であれば、30日を経過すると出荷できなくなってしまい、まだ食べられるのにもかかわらず廃棄対象になってしまうのです。
-まだ60日も賞味期限が残っているのに、もったいない!
本当にそう思います。Kuradashiでは、そうした納品期限切れの商品などを仕入れて、リーズナブルな価格で提供しています。
一方で、少しずつ変わってきている部分もあります。
2019年10月に食品ロス削減推進法が施行され、フードロスに対する世の中の意識が大きく変化しました。3分の1ルールについても、一部の小売チェーンでは2分の1ルールにするなどの対応が進んでいます。

生活者の意識も変わってきているような気がします。コンビニ/スーパーマーケットなどで「てまえどり」などの呼びかけが行われることで、「賞味期限内であれば問題ない」という理解が進んでいると感じます。コロナ禍で、飲食店で余ってしまった食品を積極的に食べようというムーブメントが起きたことで、さらにフードロス削減に対する意識が根付いてきたのではないでしょうか。
フードロス解決の鍵は、物流のデータ
-クラダシは、食品の物流に関わることでも、フードロス削減にアプローチされていますよね。
フードロスを削減するためには、倉庫での在庫管理が非常に重要です。クラダシが直接その部分を担えば、根本的なフードロス削減策に結びつくのではないかと考えています。
具体的には、通常商品(フードロスになる懸念のある商品ではないもの)の在庫管理をクラダシが担うという事業です。倉庫内にある商品の賞味期限をクラダシが管理し、倉庫にある商品全てをしっかり流通させようという試みです。
-食品メーカー側の管理コストも削減できそうな試みですね。在庫の管理をクラダシが行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
クラダシが在庫管理を担うことによって、メーカーにとってはより効率的な在庫流通が実現でき、フードロスになる可能性のある商品をいち早く再流通に切り替えることができます。
また、食品の廃棄を減らすためには、そもそも廃棄対象が発生しないように、需給予測に基づいた適切な量を作るという点が重要です。在庫管理を通じて賞味期限と売れ行きの関係性にまつわるデータを集めることが、正確な需給予測に繋がり、生産量の最適化に貢献できると考えています。
たとえば、100個の商品のうちKuradashiで流通させたものが50個あったとしたら、生産自体を50個にするべきだったということがわかります。また、Kuradashiで販売した50個が、2割引きで全て売れたのか、6割引きで全て売れたのか、ということも、適切な価格設定の材料になります。こうしたデータの蓄積をもとに、適正量と適正価格を見つけることがフードロスの削減に繋がりますし、それが食品メーカーのメリットになると考えています。
生産領域でそうしたサポートを行うビジネスは、クラダシの成長戦略の1つです。現在、事業化に向けて、さまざまな検証を行っております。

社会貢献型インターンシップで、広がる活動の輪
-クラダシは、社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」を通じて、地方創生にも取り組まれていますよね。どのような経緯でスタートしたのでしょうか
元々は、仕入れ先企業の方のご紹介でした。鹿児島にある種子島で安納芋などの仕入れを行っていた時、現地で「人手不足で収穫作業が追いつかない」という課題を伺いました。この時に考えたのが「学生をクラダシのインターン生として農家に派遣する」というアイデアです。収穫したものをKuradashiで販売し、その売上金をまたインターンシップの費用に回すという流れを構築できれば、「三方よし」の関係性を作ることができます。こうして「クラダシチャレンジ」という取り組みが始まりました。
知られていないかもしれませんが、農作物って、食べられる状態に育ったものが全て収穫できているわけではないんですよ。人手不足や、他にもさまざまな事情で収穫できない農作物もあるんです。そのようなものは、農林水産省が発表しているフードロスの対象には含まれていませんが、農家がしっかり利益を上げるためには、収穫すべき農作物をきちんと収穫することが必要です。「クラダシチャレンジ」で未収穫を減らし、収穫したものをKuradashiで販売することで、農家の販路を広げることにも繋げています。
参加者の学生さんの声としては、農業の大変さを知ることができた、地方の過疎化を目の当たりにして驚いた、という感想が多く、進路を決めるきっかけになることもあると聞きます。「農業の楽しさを実感し、その道に進みたくなった」「地方の課題解決に興味を持ち、地方の市役所職員になった」という方もいます。
「クラダシチャレンジ」で学生が農作業をすること自体は、農家をサポートする力としては小さいかもしれません。しかし、活動を通じて参加者が気付きを得て、自分にできる取り組みを始めてくれていることが、クラダシチャレンジの大きな意義だと思います。
事業の拡大が、社会課題解決の輪を広げる
-Kuradashiは、会員数がどんどん増えています。サービスを広げていくために、工夫していることはありますか。
楽しみながらお買い物をしていただくことと、生活の中に当たり前に溶け込むサービスにすることを意識しています。
Kuradashiの商品は、1時間くらいで商品が全部売り切れてしまうこともある一方、どんどん新しい商品も出てきます。そのため、宝探しのような気持ちで使ってくださっているように感じます。
ユーザーの声を取り入れる仕組みも作っています。一部のユーザーに新しいサービスや新商品を試していただき、フィードバックをいただくアンバサダー制度もその1つです。
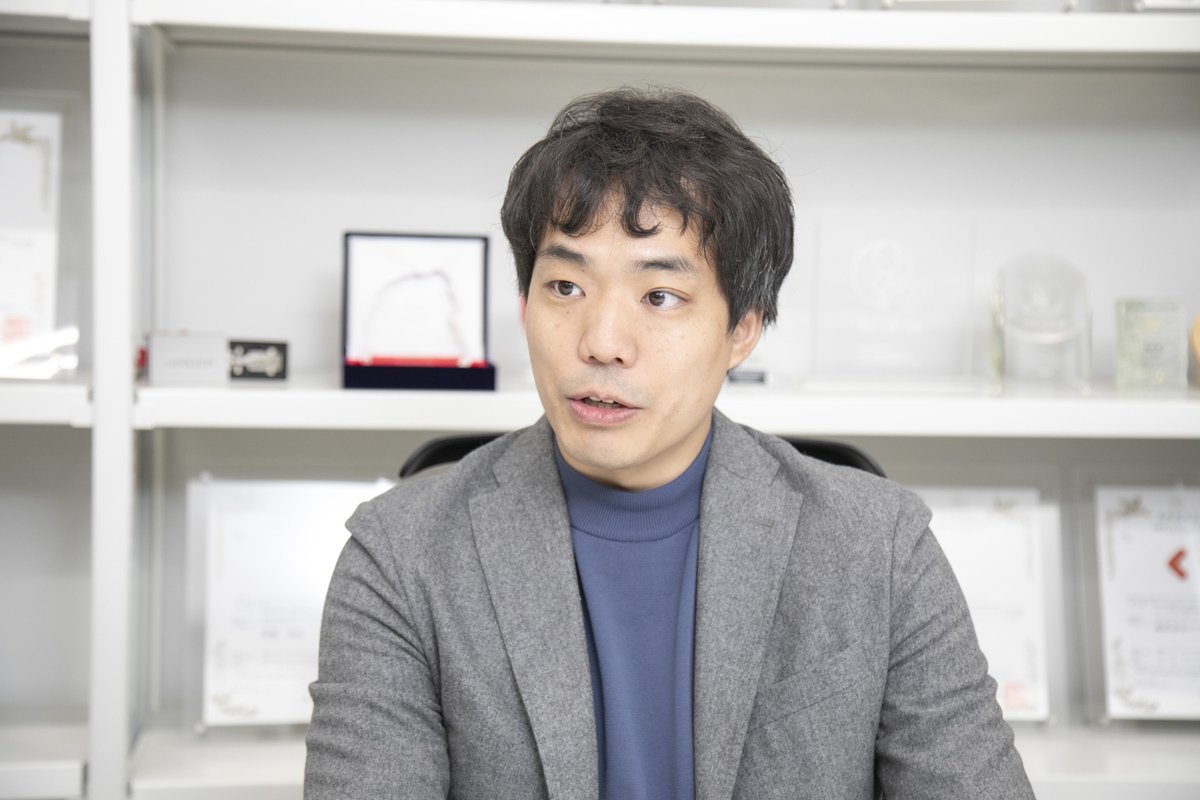
たとえば、Kuradashiの商品は、1回の購入で同じ商品がたくさん届くことが多いので、試しづらいという声があります。いろいろな商品の詰め合わせがあれば使いやすいという意見から「ロスおたすけ定期便」という商品が実現したという事例があります。
ユーザーは、30代〜50代の方が多いです。また、子育て世代の方に多くご利用いただいている印象で、毎月のように利用してくださる方もいらっしゃいます。商品としては、ビールやワインがとても人気がありますね。
会員数は、56万人を超えています(2024年9月末時点)。おトクで楽しい買い物が世の中のためになっているという仕組みが、多くの方に使っていただいているポイントだと考えています。

-クラダシは2023年に、東証グロース市場に上場しましたよね。ソーシャルグッドカンパニーとして上場する意義について、どのようにお考えでしょうか。
上場は、事業を成長させつづける使命を伴うため、ソーシャルグッドカンパニーとして上場することは、社会貢献活動の輪を継続的に広げていくと宣言するということだと捉えています。
2024年9月に開催した株主総会では、株主の方からとても熱いメッセージをいただきました。「世の中のためになる、素晴らしいサービス。誇りを持って事業を続けてください」と声をかけていただき、大変勇気づけられました。遠い地方からわざわざお越しくださった株主の方もいらっしゃり、そうした方の思いにきちんと応えていく責任を負っているのだという使命感を抱きました。
食品メーカーにとって、思いを込めて製造した商品は我が子のような存在だと思うんです。それを廃棄せざるを得ないという現状に、食品メーカーも心を痛めています。「たくさんの人に商品を届けたい」という思いを生活者に繋いでいくことは、クラダシの理念の根底にあります。そのための活動の輪に加わってくださるステークホルダーの皆さまの期待に応え、またその輪を広げるための手段、つまり、クラダシの仕組みを世の中に広めるための手段が上場なのです。
事業を大きくすることで、フードロス削減の規模も大きくできますし、クラダシチャレンジなどの活動も広げていくことができます。「ソーシャルグッドカンパニーでありつづける」ということは、公益性と経済性の両立を追求しつづけるということです。簡単に実現できることではありませんが、上場を事業拡大のステップとして、挑んでいきたいと考えています。
フードロス削減のインフラに

-社会にとって、クラダシをどのような存在にしていきたいでしょうか。
「フードロス削減のインフラ」のような存在です。今、クラダシはフードロスが発生した時のセーフティネット的な存在です。将来的にはそれだけではなく、フードロスを生まない世の中にしていくために、フードロスの発生を抑える事業も行うことで、日常の生活になくてはならない企業になりたいと考えています。
-読者の方に、どういうふうに社会と関わって欲しいと思いますか。
小さなことでも、どんなことでもいいので、とにかく行動をしてみて欲しいと思います。社会に対する課題を感じたら、それを解決する方法を考えて行動してみてください。こういう言い方をすると大きなことをしなければならないように感じるかもしれませんが、食品を選ぶ時に賞味期限の近いものを購入するというような、小さなアクションでいいんです。Kuradashiをこの記事で初めて知ったという方は、どういうものか見るだけではなく、一度でも使ってくださると嬉しいです。小さな行動の積み重ねでしかものごとは良くできないと思うので、一人ひとりが行動を起こすことが必要だと思います。
編集後記
KuradashiのECサイトを見ていたら、「本当にこれがフードロスになりそうな商品なの?」と「もったいない精神」が掻き立てられました。どの商品も、生産者の思いがこもった素敵なもの。「こんなおいしそうなものがあるんだ!」という発見にワクワクしながらお買い物が楽しめます。楽しくおトクに、社会に良い活動ができる。そんな社会貢献なら、積極的に参加したくなりますね。
取材・文:松尾千尋
撮影:樋口勇一郎
企画・編集協力:ハーチ株式会社・IDEAS FOR GOOD編集部
Money for Goodでは「#推したい会社」をテーマにnoteコンテストを開催しております!ぜひあなたの#推したい会社を熱い思いと共に投稿してください!(コンテスト募集期間:2025年1月10日(金)~2025年2月9日(日))
さまざまな企業がそれぞれに工夫をし、社会課題解決のためイノベーションをおこしています。皆さんが生活者として商品を購入するだけでなく、企業の株式を購入することで、社会課題に取り組む企業を応援することができます。株主として経済的価値を享受しながら、社会的価値も生み出せるのです。社会を良くしようとしている企業を応援してみる。あなたのできる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
「Money for Good」では読者の皆さまからの各記事への「スキ」の数に応じて、SMBC日興証券がNPO団体へ寄付を実施します。社会をより良くする一歩を、まずはここから。
Money for Goodでは、記事にまつわる内容についてのショート動画配信も始めました!こちらも是非チェックしてみてください!
【推したい会社 企業インタビュー編】
お金と人のよい循環で、明るい未来をつくる。
SMBC日興証券が行う「Money for Good」について
詳しく知りたい方はこちら▼


